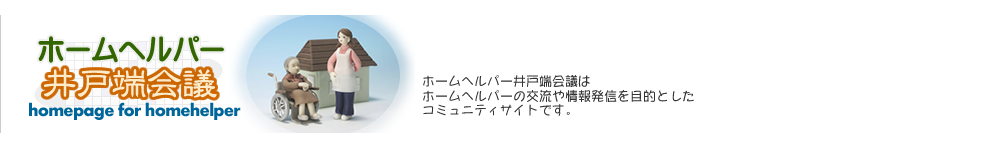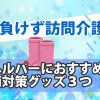要介護認定見直しの大混乱。二転三転する判断基準。
公開日: : コラム
平成21年要介護認定見直しの大混乱
平成21年度になり、要介護認定が変わりました。
具体的に言うと、大きく変更になったのは2点。
82項目あった調査項目が74項目に削減されたこと。
そして、調査が客観的な事実に基づいて該当する項目がなければ「自立」と判断するということ。
この変更により、要介護認定の結果は、従来のものよりも要介護度が軽く判定されることが明らかになりました。
この新基準での要介護認定に対する批判が集まり、ついに厚生労働省は、希望する方には新基準での要介護認定の結果を据え置き、
従来のサービスを継続して利用することができるようにした経過措置を発表するに至りました。
もちろん、現場は大混乱に陥っているわけですが、そんな要介護認定について追ってみました。
要介護認定改正までの道のり
まずは、今回の要介護認定見直しにいたるまでの経緯を振り返ってみたいと思います。
| 平成18年10月 | 第1回目の要介護認定調査検討会開催 |
| 平成20年8月 | 調査項目が82項目から74項目に絞られる |
| 平成21年1月 | 厚生労働省、新認定調査に関するパブリックコメントの募集を開始 |
| 平成21年3月 | 介護認定調査員テキストが発表。 |
| 平成21年4月 | 新方式の認定調査がスタート |
| 平成21年4月 | 要介護認定見直し検討会が開催。 認定基準に不満があれば現在と同じサービスが利用できる経過措置が発表。 厚生労働省が、要介護認定による判定結果が軽くなるように誘導し給付費の抑制を行うようにした内部文書の存在を発表。 |
そもそもの見直しの発端は、調査項目が多くて煩雑であるということと、
調査員によって調査の結果にバラつきが大きいというものでした。
ということで、モデル事業などを通して長い時間をかけ、新基準による介護認定システムができるに至りました。
しかし、この要介護認定には要介護度を軽く判定させるための仕掛けがありました。
事実だけに基づいた調査
今回の改定の大きな変更点は、客観的事実基づいた調査のみを行うということです。
たとえば、頭髪がない人に関しては整髪についての調査は、その人の持つ能力は一切問わず、必ず「自立」となります。
薬の内服も、間違った薬を飲んでいても薬を飲む動作ができていればその内容を問わず「自立」と判定されます。
批判を受けた厚生労働省は3月にこの「自立」という表現を「介助されていない」という表記に変更しましたが、
ただ、従来の調査結果と比較した場合、軽度に判定されることは目に見えています。
さらに、厚生労働省では、要介護1(要支援2)相当の該当者のうち、
その7割を要支援2に振り分けるようにという内部文書も存在し、
意図的な給付費抑制を行おうとしていたことも明らかになりました。
また、調査項目での不足に関しては、特記事項の記載が重要になるということでしたが、
自由記入欄の特記事項の内容こそ、認定調査員によるバラつきが最も大きく出るものであり、
調査員によるバラつきを少なくするという今回の要介護認定の見直しの趣旨から大きく外れています。
自分も業務上、要介護認定に立ち会うことが何度かありましたが、
調査員の方はみなテキストを何度も何度も確認しながら、テキストに対してかなり神経質な様子で聞き取りを行っていました。
けれど、その肝心な特記事項の聞き取りに関しては、質問方法や介護者からの情報の引き出し方に大きな差があったというのが率直な印象です。
突然の経過措置。取り残される利用者。
経過措置が発表され、利用者がとる選択肢が4つ用意されました。
1.新基準の要介護認定の結果を受け入れる。
2.従来より要介護度が軽く判定されても、要介護度は変更しない(重度にはなる)。
3.従来より要介護度が重く判定されても、要介護度は変更しない(軽度にはなる)。
4.従来より要介護度が重く判定されても軽く判定されても現在の要介護度のまま変更しない。
利用者はこの4つのいずれかを選択しなければいけないのですが、
これを理解するというのも実は非常に難しいことです。
もちろん、軽度に判定されることで、支給限度額が少なくなり、
現在利用しているサービスが利用できなくなるという危険性もあります。
さらに、自立に判定された場合、サービス自体が利用できなくなります。
当然、選択肢としては、2.か4.を選択するケースが圧倒的に多数になります。
そうすると、介護保険の本来の目的である自立支援というものから大きく逸脱してしまいます。
現在、包括で働いているので、この経過措置についての聞き取りなども行っているのですが、
要介護度が軽くなると、家族にほめてもらえるから、要介護度が軽くなると嬉しい、と話す方(要支援2)もいらっしゃいました。
けれど、現在の要支援2が要支援1になるだけなら、現在のサービスも継続して使えるし、自己負担も少なくなるので嬉しいことですが、
これが自立と判定されるとサービスが利用できなくなるわけですから、それは避けたい、と。
結局、今と同じサービスが利用できるようにと、要介護度を変更しないという経過措置の適用を選ばれました。
要介護度という誰にでもわかる共通の物差しを通して、必要なサービスを提供していくはずの介護保険。
今回の見直しで、その物差しの大きなゆがみが目に見えるようになり、
将来、介護が必要になったときに、本当に必要なサービスが利用できるのか、という不安が大きく広がっています。
厚生労働省では、今回の要介護認定の検証を行った後に結論を出すということでしたが、
果たしてどうなることでしょうか。
現場で働くみなさんが、実際の状態像と認定結果とのギャップをもっとも肌で感じることのできる立場にあると思いますので、
そういった情報を蓄積して、何らかの形で意見としてまとめていくことも大切なのかもしれません。
新基準の要介護認定の問題点やシュミレーションに関しては、以下のサイトに掲載されていますので、興味のある方はご覧下さい。
介護保険制度ウォッチング ~介護保険を見守る~
平成21年5月9日掲載
追記
問題だらけの要介護認定は本格的に見直しが行われ、平成21年10月申請分以降には、また新しい基準での要介護認定が適用されることになりました。
10月以降の認定調査は、調査員がその目で確認できた事実、つまり客観的事実だけを判断するのではなく、
調査員の推測も含まれる「以前の認定調査の基準」が適用されることになりました。
すったもんだのあげく、今回の目的であった調査員の質でばらつきの生まれる認定調査に再びたどり着く結果となったわけです。
平成21年11月4日掲載
アドセンス336
関連記事
-

どっちがお得?ホームヘルパー2級養成講座と介護職員初任者研修。
ホームヘルパー2級養成講座と介護職員初任者研修の比較。 すでにお伝えしている通り、これまで介護の
-
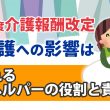
どう変わる?訪問介護。平成30年介護報酬改定はホームヘルパーに何を望むのか?
平成30年度、介護報酬が改定されます! ご存知の方も多いかと思いますが、平成30年4月に介
-
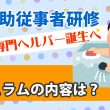
生活援助従事者研修課程、59時間カリキュラムの全容。生活援助専門ホームヘルパーの養成課程。
この記事のまとめ ・生活援助中心型サービスの担い手として、生活援助従事者研修課程を創設
-
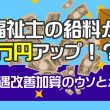
介護福祉士の給料が8万円増えるって本当?新しい処遇改善加算のウソと本当。
介護福祉士の給料が月8万円増える、という噂の正体 新しい経済政策パッケージ 「
-

ホームヘルパーになるには(資格の取得と就職について)
ホームヘルパーになるには これからホームヘルパーを目指したいという人のために、ホーム
-

平成26年介護報酬改定。消費増税に伴う介護報酬の改定の概要。
消費税増税に伴う平成26年介護報酬改定の概要 平成26年4月に消費税の増税が行われます
-
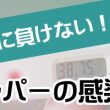
インフルエンザ対策!ホームヘルパーの感染予防。予防接種は?罹患者への訪問はどうする?
例年猛威を振るうインフルエンザ。 インフルエンザの集団感染で入退所やショートステイ受
-
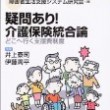
介護保険と支援費制度の統合論、そのねらいは
介護保険+支援費制度=??? 連日、メディアを騒がす介護保険の抜本改革のニュース。 歯止めの
-

訪問介護の自己負担が2割になる人、ならない人。
平成27年4月に行われた介護保険法の改正。 すでに新しい報酬単価が適応され、すでに日常生活自立支援
-

訪問介護の基本報酬、増えたのは1単位だけ!?逆風の報酬改定を斬る。
令和3年4月介護報酬改定、訪問介護はどうなる? 令和3年4月、介護保険の報酬単価が改